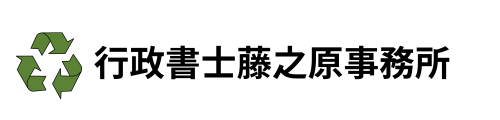パソコンで作成できる⁉自筆証書遺言作成のポイントとは?
遺言書の重要性と書き方のポイント
遺言書とは、遺言者が死亡した後に、その財産をどのように相続させるかを決めるための書面です。遺言書を作成しておくと、相続人同士のトラブルを防ぐことができます。
しかし、遺言書の書き方を間違えると、無効になってしまう可能性があります。そのため、遺言書を作成する場合、注意が必要です。
■遺言書を作成しないことで起こるトラブル
遺言書を作成していない場合、相続は法律で定められた相続分に基づいて行われます。法律で定められた相続分は、必ずしも遺言者が望む相続分と一致するとは限りません。
例えば、遺言者が長男に財産をすべて相続させたいと考えていた場合、遺言書を作成していないと、長男を含むすべての相続人が遺産を均等に相続することになります。
このような場合、遺言者が望まない相続分によって、相続人同士のトラブルが起こる可能性があります。
■自筆証書遺言の変化
民法の改正により、2019年1月13日から、自筆証書遺言の一部がパソコンでも作成可能になりました。
具体的には、財産目録について一部パソコンや通帳、登記事項証明書などのコピーで代用できるようになりました。ただし、遺言者の氏名や住所、相続人や受遺者の氏名、遺産の内容などの主要な部分は、引き続き自筆で書く必要があります。
■注意すべきポイント
自筆証書遺言を作成する場合、以下の点に注意が必要です。
・遺言者は、遺言内容の全文、日付、氏名をすべて自筆で書く必要があります。
・押印が必要です。
・遺産の内容は、具体的に記載する必要があります。
■多額の財産を残す場合の目録の列挙方法
遺産に多額の財産がある場合、遺言書にすべての財産を記載するのは困難です。このような場合は、別紙財産目録を作成して、遺言書に添付します。
別紙財産目録には、不動産や預貯金などの財産の種類や金額を、具体的に記載する必要があります。
例えば、不動産を相続させる場合、不動産の所在地や面積、評価額などを記載する必要があります。また、預貯金を相続させる場合、預貯金の口座番号や残高などを記載する必要があります。
■パソコンを使用した財産の一覧表の作成方法
パソコンを使用して財産の一覧表を作成する場合、以下の点に注意が必要です。
・各頁ごとに氏名を自署し、押印する必要があります。
・不動産や預貯金に関する情報のコピーを添付する必要があります。
・形式に注意する必要があります。
■財産目録を遺言書に一体化する際の注意事項
別紙財産目録を遺言書に一体化する場合は、以下の点に注意が必要です。
・財産目録の各頁ごとに氏名を自署し、押印する必要があります。
・変更や訂正があった場合は、特定の手続きが必要になります。
■目録の記載変更時の手続きと注意点
別紙財産目録の記載を変更または訂正する場合は、以下の手続きが必要です。
・変更箇所に押印する必要があります。
・遺言書の原本に変更の旨を記載し、押印する必要があります。
■自筆証書遺言書保管制度
令和2年7月から、自筆証書遺言書を法務局に保管する「自筆証書遺言書保管制度」が始まりました。
この制度を利用すると、遺言書の紛失や偽造を防ぐことができます。また、遺言書の存在を相続人全員に知らせることができるため、相続手続きがスムーズに進む可能性があります。
■まとめ
遺言書は、遺言者が亡くなった後に、その財産をどのように相続させるかを決めるための大切な書面です。遺言書を作成しておくと、相続人同士のトラブルを防ぐことができます。
しかし、遺言書の書き方を間違えると、無効になってしまう可能性があります。そのため、遺言書を作成する場合、注意が必要です。
遺言書の書き方が不安な場合は、法律の専門家に相談することをおすすめします。
自筆証書遺言についてご不明な点等ございましたら、当事務所までご相談下さい。