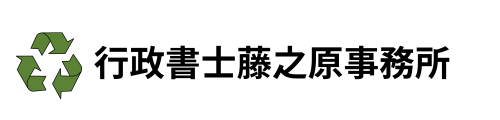過去最多769億円!相続人がいない財産。その後どうなる?
■はじめに
遺産相続において、相続人がいない場合の最終的な手続きとその影響について、簡潔に紹介します。
相続人がいない場合、相続財産は、相続財産清算人によって管理されます。相続財産清算人は、まず被相続人の債権者への弁済を行います。債権者への弁済が終わると、残った相続財産は、受遺者や特別縁故者へ分配されます。受遺者や特別縁故者がいない場合、残った相続財産は、国庫に帰属します。
■遺産相続の背景
近年、遺産相続の急増が問題になっています。その背景には、以下の2つの要因が考えられます。
・遺産総額の増加
過去10年で、遺産総額は約1.5倍に増加しています。これは、少子高齢化による人口減少や、高齢者の資産形成の進展などが原因と考えられます。
・身寄りのいない人の増加
厚生労働省の調査によると、2020年の65歳以上の未婚者の割合は、男性28.4%、女性17.8%に達しています。また、2021年の65歳以上の単身世帯の割合は、男性15%、女性22.1%に達しています。
■国庫帰属相続財産の増加
国庫帰属相続財産とは、相続人がいないために国庫に帰属した遺産のことです。2022年度の国庫帰属相続財産は、前年度より約122億円も増加し、768億9千万円余となりました。これは、2013年度との比較で最も多い金額です。
国庫帰属相続財産の増加は、以下の2つの要因が考えられます。
・遺言書の作成率の低さ
法務省の司法統計調査によると、2022年の65歳~69歳の自筆証書遺言書作成率は3.6%、公正証書遺言の作成率は2,7%です。
・未婚者や単身世帯の増加
未婚者や単身世帯の増加に伴い、相続人がいないケースが増えていることが、国庫帰属相続財産の増加につながっています。
■遺言書の重要性
遺言書は、相続人のいない場合に、遺産の処分を決めるための重要な書類です。遺言書がない場合、相続財産は、民法の規定に従って、相続人に分配されます。
相続人がいない場合は、以下の手続きが行われます。
・相続財産清算人の選任
相続財産清算人は、相続人がいない場合に、相続財産を管理して精算する役割を担います。相続財産清算人は、利害関係人または検察官が家庭裁判所に申立てを行い、裁判所が選任します。
・債権者への弁済
相続財産清算人は、まず被相続人の債権者への弁済を行います。債権者への弁済が終わると、残った相続財産は、受遺者や特別縁故者へ分配されます。
・相続財産の帰属
受遺者や特別縁故者がいない場合、残った相続財産は、国庫に帰属します。
■相続放棄や身寄りのない場合の手続き
相続人が全員相続放棄するか、身寄りがない場合、以下の手続きが行われます。
・相続放棄の申述
相続人が相続放棄する場合は、被相続人の死亡を知った日から3ヶ月以内に、家庭裁判所に相続放棄の申述を行う必要があります。
・相続財産清算人の選任
相続人が全員相続放棄した場合、または身寄りがない場合は、相続財産清算人の選任手続きが行われます。
■地域への遺産活用
身寄りのない人の遺産は、地域に役立てることも可能です。
例えば、公益財団法人「県みらい基金」は、遺産を地域の公共的活動に活用する基金です。この基金では、遺産を寄付した人の名前を基金に残し、遺産の活用状況を公表することで、遺産の社会的意義を高めています。
また、遺言書に「公益団体に寄付する」という内容を記載することで、遺産を地域に還元することも可能です。
■未婚者や少子高齢化の影響
近年、未婚者や単身世帯の増加に伴い、相続人がいないケースが増えています。
厚生労働省の人口動態統計によると、2022年の死亡者数は156万人で前年度より9%増加しています。この死亡者数の増加は、少子高齢化による人口減少や、平均寿命の延伸などが原因と考えられます。
相続人がいない場合、相続財産は、相続財産清算人によって管理され、債権者への弁済や、受遺者や特別縁故者への分配が行われます。しかし、受遺者や特別縁故者がいない場合は、相続財産は国庫に帰属します。
■終活と死後の備え
遺言書の作成や、相続に関する相談など、死後の備えは、専門職の力を借りることが大切です。
遺言書の作成は、専門家に依頼するのが一般的です。また、相続税に関する相談は、税理士などの専門家に相談するとよいでしょう。
■まとめ
近年、遺産相続の急増が問題になっています。相続人がいない場合は、相続財産は、相続財産清算人によって管理され、債権者への弁済や、受遺者や特別縁故者への分配が行われます。しかし、受遺者や特別縁故者がいない場合は、相続財産は国庫に帰属します。
遺言書の作成や、相続に関する相談など、死後の備えは、専門職の力を借りることが大切です。
遺言書を作成することで、相続人がいない場合に、遺産の処分を決めることができます。また、相続に関する相談をすることで、相続の手続きや税金などの問題について、専門家のアドバイスを受けることができます。
遺言の作成についてご不明な点等ございましたら、当事務所までご相談下さい。