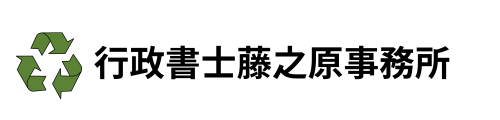行方不明の弟が相続を阻む!どう対処するか?
■はじめに
Aさんは、70代の父を亡くしました。Aさんは父と母と暮らしていました。父の死後、Aさんは母と遺産分割協議を行う予定でした。
ところが、Aさんの弟であるBさんが数年前から妻子を置いたまま行方不明です。Bさんも相続人であるため、AさんはBの居場所を探し、遺産分割協議に参加してもらおうとしましたが、Bの居場所はわからず、遺産分割協議が進まない状況です。
相続の発生と相続人の現状
Aさんの父の相続は、以下のとおりです。
相続人:母、Aさん(長女)、Bさん(弟)
相続財産:不動産(1億円)、現預金(1,000万円)
Aさんは、父の遺産を利用して、経済的な厳しさを解消したいと考えていました。しかし、Bが行方不明であることから、遺産分割協議が進まず、Aさんの希望はかなえられそうにありません。
■遺産分割協議の必要性と障害
遺産分割協議とは、相続人間で遺産をどのように分けるかを話し合う手続きです。相続財産を取得するには、原則としてこの手続きが必要となります。
Aさんの場合、Bが行方不明であるため、Bの同意を得ずに遺産分割協議を進めることはできません。そのため、Bの居場所を探し、遺産分割協議に参加してもらうことが必要です。
■行方不明者の対処方法
行方不明の相続人がいる場合、以下の対処方法が考えられます。
・連絡先を特定する
まずは、Bの連絡先を特定することが第一歩です。Bの戸籍の附票を取得して住所を特定します。また、Bの友人や知人、過去の勤務先などに連絡をして、Bの居場所を探すことができます。
・連絡しても返事が来ない場合
Bに連絡しても返事が来ない場合は、Bの住所に直接訪問したり、公示催告(行方不明者や不在者に対して、官報や新聞などの公示機関に催告文を掲載して、その者の所在を明らかにする手続き)や、家庭裁判所に遺産分割調停を申し立てを行います。
・連絡先に住んでいなかった場合
戸籍の附票に記載されていた住所にBが住んでいなかった場合は、Bが転居した可能性もあります。Bの旧居の管理会社や自治体に問い合わせることで、Bの転居先を探すか、家庭裁判所に対して不在者財産管理人の選任を行います。
■不在者財産管理人の選任
Bの居場所がどうしてもわからない場合は、家庭裁判所に「不在者財産管理人」の選任を申し立てることができます。不在者財産管理人は、行方不明者の代理人として、行方不明者の財産を管理する役割を担います。
不在者財産管理人の選任手続きは、以下のとおりです。
不在者財産管理人選任の申立書を家庭裁判所に提出します。
申立書には、以下の書類を添付します。
・不在者の戸籍謄本
・申立人の戸籍謄本
・不在者財産管理人候補者の氏名、住所、年齢、職業等
家庭裁判所は、申立書や添付書類を審査し、不在者財産管理人を選任します。
■失踪宣告の申立て
Bが7年以上行方不明である場合は、家庭裁判所に「失踪宣告」の申立てをすることができます。失踪宣告が確定すると、Bは死亡したものとみなされます。
失踪宣告の申立て手続きは、以下のとおりです。
失踪宣告の申立書を家庭裁判所に提出します。
申立書には、以下の書類を添付します。
・不在者の戸籍謄本
・申立人の戸籍謄本
・不在者の失踪の事実を証明する資料(失踪宣告申立書の記載例)
家庭裁判所は、申立書や添付書類を審査し、失踪宣告の審判をします。
■不在者財産管理と失踪宣告の選択
不在者財産管理と失踪宣告は、どちらも行方不明の相続人に対処するための手続きですが、それぞれにメリットとデメリットがあります。
・不在者財産管理のメリット
Bの意思や同意がなくても遺産分割協議を進めることができる
Bの財産を適切に管理することができる
・不在者財産管理のデメリット
不在者財産管理人の選任や管理に費用がかかる
Bが再び出現した場合、不在者財産管理人の行った手続きを変更する必要がある
必ず法定相続分以上を取得する内容でなければならない。
・失踪宣告のメリット
Bの意思や同意がなくても遺産分割協議を進めることができる
不在者財産管理の費用や手間がかからない
・失踪宣告のデメリット
Bが再び出現した場合、遺産分割協議をやり直す必要がある
どちらの手続きを選ぶかは、Bの行方不明の状況や、遺産分割を進めたいタイミングなどによって、判断する必要があります。
■法定相続分に基づく進行方法
Bが行方不明である場合、遺産分割協議が進まない場合は、法定相続分に基づいて遺産を分割するという方法もあります。
法定相続分とは、法律で定められた相続人の割合です。Aさんの父の相続の場合、母1/2、AさんとBの法定相続分は、それぞれ1/4となります。
法定相続分に基づいて遺産を分割する場合は、遺産分割協議書を作成する必要はありません。ただし、遺産分割の対象となる財産や、それぞれの相続人が取得する財産の割合などを明確にしておく必要があります。
また、不動産の場合は共有となりますので、共有の状態では売却はできません。
■問題を先送りせず解決へのアプローチ
行方不明の相続人がいる場合、遺産分割協議が進まないままに放置しておくと、さまざまなトラブルに発展する可能性があります。
たとえば、AさんがBの財産を勝手に処分した場合、Bが再び出現した場合に、Bから損害賠償を請求される可能性があります。
また、AさんがBの財産を相続したとしても、Bが再び出現した場合、遺産分割協議をやり直す必要がある場合があります。
そのため、行方不明の相続人がいる場合でも、早めに適切な対応をとることが大切です。
■まとめ
行方不明の相続人がいる場合、遺産分割が困難になることがあります。
不在者財産管理や失踪宣告などの手続きを活用することで、遺産分割を進めることができます。
また、法定相続分に基づいて遺産を分割するという方法もあります。
行方不明の相続人がいる場合は、早めに専門家に相談して、適切な対応をとるようにしましょう。