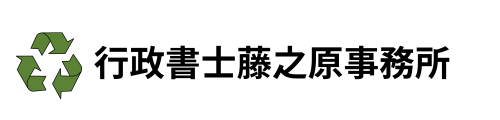亡くなった家族が連帯保証人!その相続を回避する方法とは?
■はじめに
親や兄弟が亡くなり、相続が発生する中で、思わぬ問題に直面することがあります。その一つが、被相続人が第三者の借金の連帯保証人になっていた場合です。
連帯保証人とは、主債務者が返済不能となった場合に、その代わりに債務を返済する義務を負う人のことですが、相続が発生すると、被相続人の連帯保証人としての地位も相続人に引き継がれることになります。
■相続の対象となるもの
相続は、被相続人の遺産を相続人が引き継ぐ制度です。遺産には、プラスの財産だけでなく、マイナスの財産も含まれます。そのため、被相続人が連帯保証人になっていた場合、相続人は、その借金の返済義務も引き継ぐことになります。
■返済義務と法定相続分
相続人が連帯保証人の返済義務を負う場合、その負担は、法定相続分に応じて分配されます。例えば、相続人が3人いて、被相続人の借金が100万円の場合、相続人一人あたり約33万円の返済義務を負うことになります。
ただし、相続人どうしで返済義務の割合を変更する取り決めをすることも可能です。しかし、その取り決めは、相続人全員の合意がなければ法的効力を持たないので注意が必要です。
■相続税と債務控除の関係
相続税の計算においては、債務は相続財産から控除することができます。しかし、債務の額を正確に把握することが難しいことや、債務の返済が相続税の納付期限を超える場合もあるため、注意が必要です。
■借金の返済免除の手段: 相続放棄
相続人が連帯保証人の地位を回避するための手段として、相続放棄があります。相続放棄とは、被相続人の遺産を一切相続しないことを宣言する手続きです。
相続放棄をすると、被相続人のプラスの財産だけでなく、マイナスの財産も一切相続しないことになります。そのため、連帯保証人の地位も回避することができます。
■相続放棄のプロセスと注意点
相続放棄の手続きは、家庭裁判所に相続放棄の申述書を提出することで行います。相続放棄の申述期間は、被相続人の死亡を知った日から3ヶ月以内です。
相続放棄をすると、被相続人のプラスの財産だけでなく、マイナスの財産も一切相続しないことになるため、慎重に検討する必要があります。
■知らないうちの連帯保証人の発覚と対処法
相続人が後から連帯保証人であったことを知った場合、相続放棄の申述期間が過ぎている可能性があります。
そのような場合は、期限経過後でも相続放棄の認められる場合があるため、専門家へ相談することをおすすめします。
■専門家に相談する重要性
相続放棄や連帯保証は、複雑な法律問題を伴うため、専門家の助言を受けることが重要です。
専門家は、相続放棄や連帯保証に関する豊富な知識と経験を有しており、適切なアドバイスやサポートを受けることができます。
■まとめ
相続で連帯保証人になるリスクは、決して少なくありません。そのため、相続が発生する前に、被相続人が連帯保証人になっている可能性があるかどうかを確認しておくことが大切です。
また、相続が発生した場合は、早めに専門家に相談し、適切な対応を検討するようにしましょう。