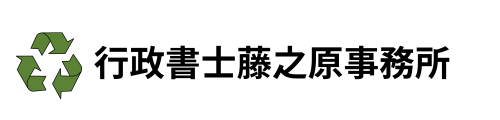認知症の母が相続人に!相続手続きの注意点と解決策とは?
父が亡くなり、相続人が私、認知症の母、未成年の弟の子供たちである状況を想定して、認知症の母の相続手続きにおけるポイントと解決策をまとめました。
■はじめに
認知症の相続手続きは、通常の相続手続きとは異なる点が多く、注意が必要です。
まず、認知症の相続人は、遺産分割協議に参加することができません。遺産分割協議は、相続人全員の合意によって成立するため、認知症の相続人が参加できないと、遺産分割協議が成立せず、相続手続きが進まない可能性があります。
また、認知症の相続人は、遺産分割協議に参加できないだけでなく、遺産の管理や処分もできません。そのため、認知症の相続人の財産を守るために、成年後見制度を利用したり、特別代理人を選任したりするなどの対策が必要です。
■相続放棄とは?
認知症の相続人が遺産分割協議に参加できない場合、相続放棄を検討することもできます。相続放棄とは、相続権を放棄する手続きです。相続放棄をすると、相続財産を取得することができなくなり、相続税もかかりません。
ただし、相続放棄は、相続開始を知った日から3か月以内に家庭裁判所に申立てを行う必要があります。また、相続放棄をすると、相続財産だけでなく、相続債務もすべて放棄することになります。
■後見開始申立手続を検討する理由
認知症の相続人が遺産分割協議に参加できない場合、成年後見制度を利用することもできます。成年後見制度とは、認知症や精神障害などで判断能力が不十分な人に、家庭裁判所が後見人を選任し、財産管理や身上監護を行う制度です。
後見人が選任されると、認知症の相続人の財産管理や遺産分割協議への参加が可能になります。また、後見人が選任されると、認知症の相続人の財産を守るために、遺産分割協議の際に、特別代理人を選任することもできます。
■利益相反が生じる場合の特別代理人選任手続
後見人と被後見人の利益が相反する場合、特別代理人を選任する必要があります。特別代理人は、後見人とは別に、家庭裁判所が選任する代理人です。
特別代理人は、後見人とは別に、被後見人の利益を代表して、遺産分割協議に参加したり、遺産の管理や処分を行うことができます。
■未成年者が相続人の場合の特別代理人選任手続
未成年者が相続人である場合、親権者が未成年者の代理人として、遺産分割協議に参加したり、遺産の管理や処分を行うことができます。
ただし、親権者と未成年者の利益が相反する場合、特別代理人を選任する必要があります。
■生前に遺言書や信託契約の検討
認知症の相続手続きをスムーズに進めるためには、生前に遺言書や信託契約を作成しておくことが望ましいです。
遺言書を作成しておけば、遺産分割協議をする必要がなくなり、相続手続きが簡略化されます。また、信託契約を作成しておけば、認知症になっても、信託契約に基づいて、財産を管理や処分することができます。
■まとめ
認知症の母の相続手続きは、通常の相続手続きとは異なる点が多く、注意が必要です。
認知症の相続人が遺産分割協議に参加できない場合、相続放棄や成年後見制度の利用、特別代理人選任手続などの対策を検討する必要があります。また、生前に遺言書や信託契約を作成しておくことでも、相続手続きをスムーズに進めることができます。
認知症の相続手続きは、複雑で難しいものです。専門家に相談しながら、適切な対策を検討することが大切です。