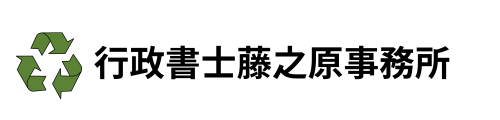知らなかった?相続人不在時の葬儀費用の支払いはどうすればよい?
■はじめに
事例紹介
私の大叔母が先日亡くなりました。生前に結婚しておらず、子供もいなかったため、法定相続人は存在しません。大叔母は生前に多少の預貯金を持っていました。
このような場合、葬儀費用をどのように処理すればよいのでしょうか?
相続人不存在時の財産処理の難しさ
相続人が存在しない場合、財産の管理や処分が難しくなります。特に、葬儀費用のような緊急性の高い支出は、迅速な対応が必要となるため、より複雑な問題となります。
問題点
・【意思決定者不在】
遺産をどのように管理・処分するかを決定する人がいないため、手続きが遅延したり、適切な処理が行われない可能性があります。
・【手続きの複雑化】
相続財産清算人の選任、権限外行為許可の申立など、通常よりも多くの法的な手続きが必要となります。
時間と費用: 専門家のサポートが必要になる場合が多く、時間と費用がかかります。
以上のような理由から、相続人が存在しない場合には、財産の管理や処分がより複雑な問題となります。特に、葬儀費用のような緊急性の高い支出に関しては、迅速な対応が求められますが、法的な手続きや規定に従う必要があります。
その為、生前からの準備が重要となります。
以下、下記の内容で進めていきます。
1.生前の準備:遺言書と死後事務委任契約
2.遺産管理者の選任手続き:相続財産清算人の選任
3.利害関係人としての条件と申立手続き:
4. 相続財産清算人への権限外行為許可の申立て
5. まとめ
1.生前の準備:遺言書と死後事務委任契約
遺言書の作成方法と効力
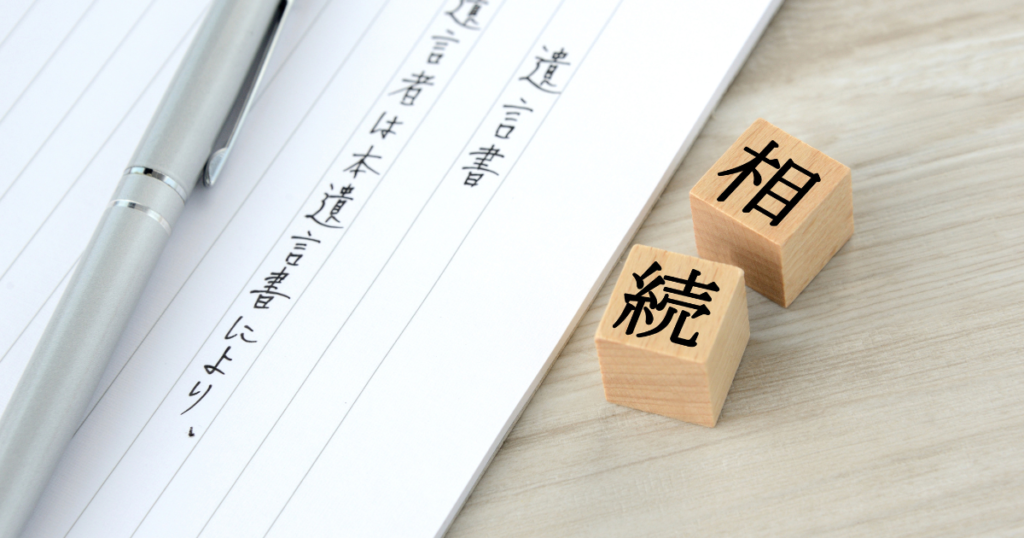
生前に遺言書を作成しておけば、遺産の分配方法だけでなく、葬儀費用についても具体的な指示を残すことができます。
遺言書において、葬儀費用の支払い方法や負担者を指定することができます。特定の財産や預貯金を葬儀費用に充てるよう指示することができます。
死後事務委任契約の締結と内容
死後事務委任契約は、死後の事務処理を特定の者に委託する契約です。この契約によって、故人の死後に行われる事務処理や手続きを事前に特定の者に委任することができます。具体的には、葬儀の形式や費用、納骨先などの事項を含む、死後の手続きに関する様々な事務を委託することが可能です。
死後事務委任契約は、遺言書とは異なり、死後の手続きや遺産の管理、葬儀や墓地の手配などの具体的な事務に焦点を当てています。このような契約を締結することで、故人の意思や希望を遺族や関係者により明確に伝えることができ、円滑な事務処理が可能となります。
ただし、死後事務委任契約も遺言書と同様に、法律の定める条件や手続きに則って作成する必要があります。そのため、専門家のアドバイスや助言を受けながら、適切に契約を作成することが重要です。
2.遺産管理者の選任手続き:相続財産清算人の選任
相続財産清算人の役割と選任手続き

相続人がいない場合は、家庭裁判所に申立てを行い、相続財産清算人を選任する必要があります。相続財産清算人は、遺産の調査、管理、処分、債務の弁済などを行います。
相続財産清算人は、家庭裁判所によって選任されるため、申立てが必要であり、適格な候補者が選任されるまで一定の手続きが必要です。
相続財産清算人は法律上、特別の資格が必要との規定はありません。
被相続人との関係や利害関係の有無などを考慮して、相続財産を清算するのに最も適任と認められる人が選ばれます。
一般的には家庭裁判所が地域の弁護士や司法書士などを選任することが多いようです。
3.利害関係人としての条件と申立手続き

相続財産清算人の選任申立は、利害関係人であれば誰でも行うことができます。利害関係人とは、相続財産において法律上の利害を有する者のことを指します。一般的には、故人の配偶者や子供、親族、債権者、債務者、特別縁故者などが利害関係人に該当します。
利害関係人は、家庭裁判所に対して相続財産清算人の選任申立を行うことができます。申立の際には、申立人が利害関係人であることを示すための必要書類や証明書を提出する必要があります。
ただし、利害関係人であっても、適格な選任申立かどうかは家庭裁判所が判断します。家庭裁判所は、申立人が相続財産の利害関係を有していることを確認した上で、適切な判断を行います。
したがって、相続財産清算人の選任申立を行うためには、利害関係人であれば誰でも申立を行うことができますが、申立人が相続財産に関する利害関係を有していることが必要です。
申立書には、申立人の住所、氏名、相続人不存在の事実、遺産の内容などを記載する必要があります。
4.相続財産清算人への権限外行為許可の申立て
相続財産清算人の権限と許可申立ての必要性
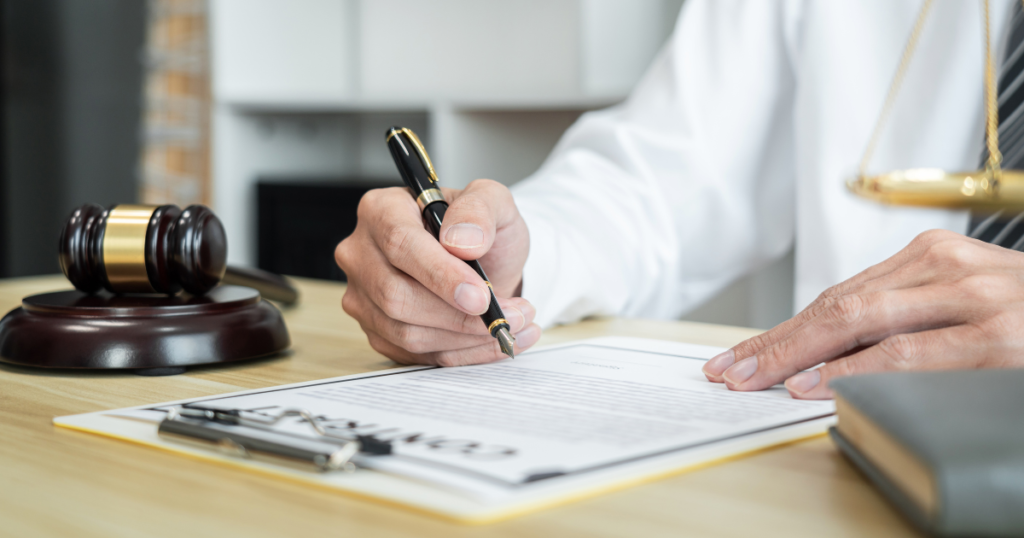
相続財産清算人は、基本的に遺産の管理・処分に関する権限のみを持ちます。葬儀費用等の支出は、権限外行為となるため、家庭裁判所の許可が必要です。
権限外行為とは、相続財産清算人の権限に含まれていない特定の行為を指します。葬儀費用等の支出は、通常の相続財産の管理や処分とは異なるため、相続財産清算人の権限の範囲外とされます。
そのため、葬儀費用等の支出を行う場合には、家庭裁判所に権限外行為の許可を申請する必要があります。家庭裁判所は、申請内容や事情を審査した上で、許可を与えるかどうかを判断します。特に葬儀費用は緊急かつ必要な支出であるため、迅速な審査が求められます。
したがって、相続財産清算人が葬儀費用等の支出を行う際には、事前に家庭裁判所の許可を得ることが必要です。
主な権限外行為は次のとおりです。
① 不動産の処分(建物の取り壊しを含む。)
② 動産の売却、譲渡、贈与、廃棄(自動車の売却や廃車手続きを含む。)
③ゴルフ会員権、株券などの売却
④永代供養料の支払い、墓地などの購入費用
⑤出資金持分譲渡契約
⑥訴訟の提起、訴えの取下げ、訴訟上の和解、調停
⑦立替金の支払いや被相続人が生存していたならば当然謝礼をしたと思われる 人への謝金支払い
葬儀費用等の支出に関する許可申立ての手続きと注意点
・【許可申立手続き】
許可申立手続きは、家庭裁判所に対して行います。申立書を提出し、必要な書類や証明書を添えて申請を行います。
申立書には、支出の目的や金額、支出先など具体的な内容を記載する必要があります。
必要な書類には、葬儀の見積書や領収書、相続財産の詳細なリストなどが含まれます。
・【注意点】
申立書や書類の記載内容は正確で具体的である必要があります。支出の目的や金額、支出先などが明確に記されていることが求められます。
葬儀費用等の支出が緊急かつ必要な場合が多いため、手続きを迅速に進めることが重要です。
葬儀費用等の支出が相続財産の範囲内で相当であることを示す資料が必要です。葬儀の見積書や領収書などを準備し、提出する必要があります。
許可が得られるまで支出を行わないように注意し、家庭裁判所からの許可を待つことが重要です。支出が許可されなかった場合、その費用は相続財産から支出することができません。
以上が、葬儀費用等の支出に関する許可申立ての手続きと注意点です。申立ての際には、必要な書類や手続きを適切に行い、家庭裁判所の判断を待つようにしてください。
5.まとめ
生前の準備の重要性と遺言書・死後事務委任契約の有用性

相続人不存在時の混乱を避けるため、生前に遺言書を作成しておいたり、死後事務委任契約を締結しておくことが重要です。
・【財産の処分や負債の整理】
相続人が存在しない場合、財産の処分や負債の整理が大変複雑化します。遺言書を作成しておくことで、自分の意思に基づいて財産の処分や負債の整理を行うことができます。
・【葬儀や埋葬の希望の明確化】
遺言書や死後事務委任契約には、葬儀や埋葬の希望を明確に記載することができます。これにより、生前の希望通りに葬儀や埋葬が行われることを保証することができます。
・【財産の管理と引き継ぎ】
死後事務委任契約を締結することで、信頼できる者に財産の管理や処分を委託することができます。これにより、相続人が存在しない場合でも財産の引き継ぎがスムーズに行われます。
・【法的混乱の回避】
相続人が存在しない場合、法的な手続きが複雑化し、法的混乱が生じる可能性があります。遺言書や死後事務委任契約を作成しておくことで、法的混乱を回避することができます。
以上のように、生前に遺言書を作成しておいたり、死後事務委任契約を締結しておくことは、相続人が存在しない場合の混乱を避けるために非常に重要です。
法的な手続きには専門知識が必要となるため、専門家に相談することをお勧めします。
出典:
法務省:相続財産管理制度 [https://www.moj.go.jp/content/001324101.pdf]
国税庁:No.4132 相続人の範囲と法定相続分[https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/sozoku/4132.htm]