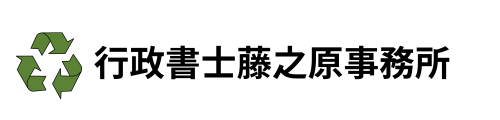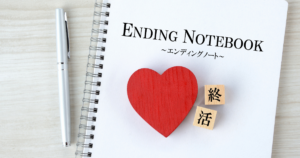東京・湾岸オフィス空室率の衝撃!再開発エリアでいったい何が?
■はじめに
東京・湾岸エリアのオフィス空室率の高止まり

東京・湾岸エリアはかつて、国際的なITビジネスの拠点として栄えましたが、現在では厳しい状況に立たされています。
特に、オフィスの空室率が高止まりし、(2023年現在、都心5区全体のオフィス空室率は4.97%。湾岸エリアの、品川シーサイドフォレスト・天王洲アイルエリアは11.91%、東日本橋・新川エリアは10.54%)再開発先進地として知られるこの地域がなぜ苦境に立たされているのでしょうか?
以下の順番で、その背景に迫ります。
1.現状の分析:湾岸エリアのオフィス市場の変遷
2.流出の理由:企業の移転要因
3.生き残り策:オフィス空室率の解消策
4.将来展望:都心のビジネス拠点の持続可能性
5.まとめ:湾岸エリアのオフィス市場の今後
1.現状の分析:湾岸エリアのオフィス市場の変遷

湾岸エリアのオフィス市場の変遷は、以下のような流れになっています。
・【バブル期の急速な発展(1980年代後半 - 1990年代初頭)」
1980年代後半から1990年代初頭にかけてのバブル期に、湾岸エリアは急速に発展しました。ウォーターフロント開発が進み、多くの企業が進出しました。特に、高度なテクノロジーを要する企業や国際的な企業が集まり、湾岸エリアは国際的なビジネス拠点としての地位を確立しました。
・【ITビジネスの拠点化(1990年代中期 - 2000年代初頭)】
1990年代中期から2000年代初頭にかけて、湾岸エリアは国際的なITビジネスの拠点としてさらに発展しました。多くのIT企業が進出し、高層ビルやモダンなオフィス施設が建設されました。湾岸エリアは、最新の技術を利用したオフィス環境やネットワークインフラの整備が進んだ場所として知られるようになりました。
・【「リーマンショックと震災の影響(2008年 - 2011年)】
2008年のリーマンショックや2011年の東日本大震災の影響を受け、湾岸エリアのオフィス市場は一時的な停滞や変化を経験しました。一部の企業が撤退し、オフィス需要が一時的に低下しました。
・【コロナ禍と働き方の変化(2020年以降)】
2020年の新型コロナウイルスのパンデミック以降、湾岸エリアのオフィス市場はさらなる変化を経験しています。リモートワークや柔軟な働き方が普及し、オフィス需要が低下しました。一部の企業はオフィスを縮小または撤退し、湾岸エリアのオフィス市場において空室率の上昇が続いています。
これらの変遷を踏まえると、湾岸エリアのオフィス市場は過去数十年間にわたって急速な発展や変化を経験してきました
2.流出の理由:企業の移転要因

湾岸エリアから企業が移転する理由は何でしょうか?
企業が湾岸エリアから移転する理由は複数ありますが、主な要因は以下の通りです。
・【コスト削減】
湾岸エリアは都心部に位置し、土地や建物の価格が比較的高い傾向があります。企業はオフィスの賃料や関連費用を削減するために、より経済的な地域へ移転することがあります。
・【アクセスの便利性】
都心部や交通ハブに近い場所への移転は、従業員やクライアントへのアクセスが容易になるため、企業にとって魅力的です。湾岸エリアが利便性に欠ける場合、移転先の選択肢が増えます。
・【働きやすい環境の確保】
ワークライフバランスや労働環境の改善が企業にとって重要な課題となっています。都心部や魅力的な街区への移転は、従業員の生活や労働環境の向上につながる場合があります。
・【テクノロジーの進化】
近年のテクノロジーの進化により、リモートワークやデジタルコミュニケーションツールの利用が一般化しています。そのため、必ずしも都心部にオフィスを構える必要がなくなり、湾岸エリアから他の地域や郊外への移転を検討する企業も増えています。
・【地域の魅力やイメージの変化】
湾岸エリアのイメージや魅力が変化した場合、企業がその地域に魅力を感じなくなる可能性があります。例えば、治安の悪化やインフラ整備の不足、地域の景観や環境の悪化などが挙げられます。
これらの要因が組み合わさり、企業が湾岸エリアから移転する理由となる場合があります。
3.生き残り策:オフィス空室率の解消策

それでは、オフィスの空室率を解消するためには、どのような施策が必要でしょうか。湾岸エリアのオフィスビルでは、大規模な改修工事や賃料値下げ、フリーレントなどの施策が取られています。これらの施策の効果や将来展望について考察します。
湾岸エリアのオフィスの空室率を解消するためには、以下のような施策が有効です。
・【改修・リニューアル】
オフィスビルの改修やリニューアルを行い、古くなった施設を現代的な設備やデザインにアップデートします。これによって、テナントの興味を引き、空室を埋めることができます。
・【賃料の見直し】
賃料を見直し、競争力のある価格設定を行うことで、テナント企業の引き込みを図ります。また、初期費用の割引や長期契約者への特典などを提供することも考慮します。
・【フリーレント期間の提供】
テナント企業に対して一定期間の家賃無料期間を提供することで、リスクを軽減し、空室を埋める動機付けを行います。
・【テナント企業へのサポート】
テナント企業に対して、移転や引っ越しのサポート、オフィス環境のカスタマイズや設備の提供などを行うことで、企業のニーズに合ったオフィススペースを提供します。
・【コミュニティ活動の促進】
地域コミュニティの形成や活性化を促進するために、オフィスビル内や周辺地域でのイベントや交流会の開催、地域資源の活用などを行います。これによって、地域の魅力が高まり、テナント企業の興味を引きます。
・【多様なオフィススペースの提供】
コワーキングスペースやフレックスオフィス、シェアオフィスなど、柔軟なオフィススペースを提供することで、様々な規模やニーズを持つ企業を受け入れることができます。
これらの施策を総合的に行うことで、湾岸エリアのオフィスの空室率を解消し、地域の活性化と持続可能なビジネス環境の確立に貢献することができます。
4.将来展望:都心のビジネス拠点の持続可能性

最後に、都心のビジネス拠点としての将来展望について考えます。
人口減少やオフィス需要の変化が今後のビジネス環境にどのような影響を与えるのか、そして湾岸エリアが持続可能なビジネス拠点としての地位を維持するためにはどうすべきかを検討します。
人口減少やオフィス需要の変化は都心のビジネス拠点の将来性に影響を与えます。
・【人口減少】
人口減少は都心部のビジネス拠点に直接的な影響を及ぼします。人口が減少すると、地域の消費やサービス需要が低下し、企業の活動やビジネスチャンスが減少する可能性があります。また、人口減少によって労働力の減少や若年層の減少が起こり、企業の人材確保や成長の妨げになることがあります。
・【オフィス需要の変化】
オフィス需要の変化も都心のビジネス拠点に大きな影響を与えます。テクノロジーの進化や働き方の変化により、リモートワークやフレックスタイム制度が普及し、オフィスの必要性や使用頻度が変化しています。これにより、オフィススペースの需要が減少する可能性があります。
以上のような要因から、都心のビジネス拠点の将来性は不確実性を増す傾向にあります。しかし、一方で都心部の魅力や利便性、交通アクセスの良さ、産業クラスターの形成など、都心部が持つ強みも依然として存在します。そのため、都心のビジネス拠点が持続可能かどうかは、これらの要因のバランスと、都市政策や企業の対応に大きく左右されることになります。
湾岸エリアが持続可能なビジネス拠点としての地位を維持するためには、以下のような取り組みが必要です。
・【多様性を促進する】
単一の産業に依存せず、多様な産業やビジネスセクターを引き付けるための施策を推進します。例えば、テクノロジー、サービス、製造、観光、エンターテイメントなど、様々な分野の企業や施設を誘致し、産業のクラスターを形成します。
・【イノベーションと技術の促進】
テクノロジーやイノベーションを支援する環境を整備し、先端技術や新たなビジネスモデルの育成を促進します。研究開発施設やスタートアップ支援の拠点を整備し、新たなビジネスチャンスを創出します。
・【持続可能な開発と環境保護】
環境負荷の低減や再生可能エネルギーの活用、廃棄物のリサイクルなど、持続可能な開発と環境保護を推進します。緑化や公共交通機関の整備、地域コミュニティの活性化など、地域全体の持続可能性を考慮した都市計画を実施します。
・【教育と人材育成の重視】
高度な人材を育成し、人材の流動性や多様性を高めるための教育プログラムや研修機会を提供します。また、地域のコミュニティと産業界とのパートナーシップを強化し、地域の人材を活かした産業の育成を図ります。
・【国際化と地域連携】
国際的なビジネス環境に適応し、外国企業やグローバルなビジネスネットワークの誘致を促進します。また、他の地域との連携を強化し、交流や共同プロジェクトを通じて相互の発展を促進します。
これらの取り組みを通じて、湾岸エリアは持続可能なビジネス拠点としての地位を維持し、地域の発展と繁栄を支えることができるでしょう。
5.まとめ:湾岸エリアのオフィス市場の今後

湾岸エリアのオフィス市場は、かつては都心部の中でも特に注目され、多くの企業が進出しました。しかし、近年では様々な要因により課題を抱える状況にあります。
現状と課題
・【空室率の上昇】
コロナ禍や働き方の変化により、オフィスの需要が低下し、空室率が上昇しています。特に、他の都心部エリアに比べて湾岸エリアの空室率は高い傾向にあります。
・【競争力の低下】
都心部の他のエリアと比べて、湾岸エリアの競争力が低下しています。賃料の高騰や利便性の低下、イメージの問題などがその要因です。
・【需要の多様化】
リモートワークの普及やフレックスタイム制度の導入など、働き方の変化により、従来のオフィススペースへの需要が変化しています。
解決策
・【オフィスの改修と多様化】
オフィスの改修やリニューアルを行い、新しい働き方に対応した柔軟なオフィススペースを提供します。また、コワーキングスペースやシェアオフィスなどの多様なオフィス形態を導入することで、様々なニーズに応えます。
・【賃料の見直しと特典の提供】
賃料の見直しや特典の提供を通じて、テナント企業の引き込みや定着を図ります。フリーレント期間の提供や設備の充実など、企業にとって魅力的な条件を提供します。
・【地域コミュニティの活性化】
地域コミュニティの活性化や地域イベントの開催を通じて、湾岸エリアの魅力を高めます。また、地域との連携やパートナーシップを強化し、地域全体の発展に貢献します。
将来への展望
・【持続可能なビジネス拠点の確立】
イノベーションや技術の導入、環境保護や持続可能な開発を推進し、湾岸エリアを持続可能なビジネス拠点として確立します。
・【多様な産業の集積】
多様な産業やビジネスセクターの集積を促進し、湾岸エリアの産業クラスターを形成します。これによって、地域の経済的な活性化を図ります。
・【国際的なビジネス拠点の強化】
グローバルなビジネス環境に適応し、外国企業や国際的なビジネスネットワークの誘致を促進します。これによって、湾岸エリアが国際的なビジネス拠点としての地位を強化します。
まとめ
湾岸エリアのオフィス市場は、人口減少やオフィス需要の変化などの課題に直面し、今後も厳しい状況が続くと予想されます。しかし、空室率の解消に向けた取り組みとして、様々なニーズへの対応、サステナビリティへの配慮、イノベーションの促進などの解決策を実行とすることと、新たな需要の喚起によって、再び活気を取り戻し、持続可能なビジネス拠点として発展していくことが期待されています。
湾岸エリアのオフィス市場は、今まさに変革の時期を迎えています。空室率の高止まりという課題を乗り越え、持続可能なビジネス拠点として生まれ変わるためには、関係者による官民一体となった取り組みが必要不可欠です。今後の湾岸エリアのさらなる発展に、期待が高まっております。
参考資料:
・東京・湾岸でオフィス空室率高止まり 再開発先進地でなにが? - NHK
・東京大規模再開発 建設ラッシュに潜む2023年問題とは - NHK クローズアップ現代 全記録
出典:
森ビル株式会社 東京23区の大規模オフィスビル市場動向調査2023
https://www.mori.co.jp/company/press/release/2023/05/20230525130000004486.html
国土交通省 土地・建設産業局 地価調査課
https://www.mlit.go.jp/totikensangyo/content/001348978.pdf
三鬼商事株式会社 オフィスレポート 東京2023
https://www.miki-shoji.co.jp/rent/assets/media/report/tokyo.pdf?1706188728